B型肝炎
大津市の内科・消化器内科の林内科クリニック|B型肝炎
B型肝炎
B型肝炎とは
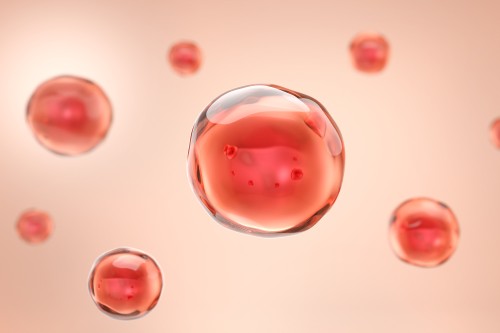
-
B型肝炎とは、B型肝炎ウイルス(HBV)に感染することで発症する肝炎のことです。
HBVは血液や体液を通じて感染します。主な感染経路としては、母子感染(垂直感染)と水平感染(主に成人後の感染)の2種類が挙げられます。 母子感染の場合、母親がB型肝炎ウイルスに感染していると、出産時の血液が赤ちゃんの体内に入ることで感染する場合があります。日本にはB型肝炎ウイルス感染者は110~140万人いると言われており、その多くは母子感染によるものですが、昭和61年(1986年)より全国規模での出生時のB型肝炎母子感染防止対策がとられているので、現在では新たな母子感染はほとんど発生していません。
水平感染の場合、以前は輸血が原因の血液感染や、予防接種での注射器の使い回し、医療従事者による針刺し事故による感染などが起きていましたが、医療環境の整備にともない現在ではほとんど発生していません。
その他の原因として性交渉による感染、刺青(タトゥー)やピアスの穴開けなどで使用する器具の使い回し、覚せい剤などの注射の回し打ちなどが挙げられ、特に多いのが性交渉による感染と言われています。
性交渉による感染では、従来の日本のウイルスとは異なる欧米型ウイルス(ジェノタイプA型)の感染例が増加しています。
B型肝炎ウイルスに
感染するとどうなるのか?

-
成人後にB型肝炎ウイルスに感染した場合(水平感染)、ほとんどはウイルスが体外に排除されるのでキャリア化することはあまりありません。ですが、母子感染も含めて3歳ごろまでに感染した場合には、ウイルスが排除されずに肝臓に感染した状態となります。
この状態で症状が現れず、一生を過ごすケースを「無症候性キャリア」と言いますが、このうち10%程度の方が症状を引き起こしてB型慢性肝炎となります。
B型慢性肝炎となってもほとんど症状は現れませんが、適切な治療を受けずに放置していると肝硬変に移行し、さらに炎症が続くと肝がんを発症するケースもあります。
なお、B型慢性肝炎とならなかった方も「非活動性キャリア」という状態になり、炎症は抑えられているもののウイルス感染は続いているので、稀に活動が活発化して肝がんを引き起こすケースもあるので注意が必要です。
B型肝炎ウイルスの検査方法
B型肝炎ウイルスの感染の有無は、血液検査で確認することができます。少量の血液を採血するだけの簡単な検査で、検査結果は1週間程度でわかります。
血液検査ではまず、「HBs抗原」と呼ばれるB型肝炎ウイルスの外殻を構成するタンパク質を確認します。
このHBs抗原が検出された場合(陽性)、血液中にB型肝炎ウイルスが存在することを意味し、初めてB型肝炎ウイルスに感染したケースと、持続感染しているケース(B型肝炎ウイルスキャリア)とに分けられます。
HBs抗原が陽性だった場合には、HBs抗体、HBc抗体、HBe抗原・抗体、HBc-IgM抗体の有無、血液中のウイルス量(HBV-DNA量)、肝機能などを調べるほか、腹部エコー検査などを実施してより詳しく感染状態を確認していきます。
B型肝炎の治療方法
B型肝炎の治療方法には、「インターフェロン(IFN)療法」や、核酸アナログ製剤を用いた「抗ウイルス療法」などがあります。ただし、これらの治療を行っても体からB型肝炎ウイルスを完全に排除することはできないため、十分な効果が得られなかった場合には「肝庇護療法」などを行って病状の進行を抑制したり、遅らせたりする必要があります。
なお、インターフェロン療法や核酸アナログ製剤治療は、医療費助成の対象となります。助成を受けた場合、その方の世帯所得に応じて自己負担1~2万円程度で治療が受けられます。
インターフェロン療法
インターフェロン療法とは、体内の免疫力を高め、ウイルスの活動を鎮静化させるインターフェロンα・βを注射で補う方法です。
核酸アナログ製剤治療
B型肝炎ウイルスの増殖が抑制できる内服薬で、薬の効果でウイルス量を低下させて肝炎を鎮静化させます。
肝庇護療法
肝庇護薬を用いて肝炎を鎮静化させる方法です。肝細胞の破壊を抑えることで、B型慢性肝炎から肝硬変への移行を抑制したり、遅らせたりすることが可能となります。