C型肝炎
大津市の内科・消化器内科の林内科クリニック|C型肝炎
C型肝炎
C型肝炎とは?
C型肝炎とは、C型肝炎ウイルス(HCV)に感染することで起こる肝炎です。C型肝炎ウイルスに感染した方のうち、70%程度が持続感染(キャリア化)してC型慢性肝炎になるとされています。
C型慢性肝炎ではほとんど自覚症状は現れませんが、適切な治療を受けずに放置していると、肝臓の組織が破壊されて肝硬変に移行し、さらに時間が経過すると肝がんになる可能性があります。日本では100人に1~2人の割合でC型慢性肝炎患者・C型肝炎ウイルスキャリアがいるとされており、「21世紀の国民病」とも言われています。
C型肝炎ウイルスは、B型肝炎ウイルスと比べて感染力が弱いため、性交渉で感染することはあまりありません。また、母子感染の確率も低いとされています。
C型肝炎ウイルスは主に体液や血液などを介して感染します。昭和64年/平成元年(1989年)にC型肝炎ウイルスが発見されるまでは、感染者の血液を用いた輸血や血液製剤、汚染された注射器・注射針による医療行為などで感染していましたが、医療環境の整備にともない現在では医療行為による感染はまず起こりません。
現在、考えられる感染経路としては、刺青(タトゥー)やピアスの穴開けなどで使用する器具の使い回しや、覚せい剤などの注射の回し打ちなどが挙げられます。
C型肝炎ウイルスに
感染するとどうなるのか?
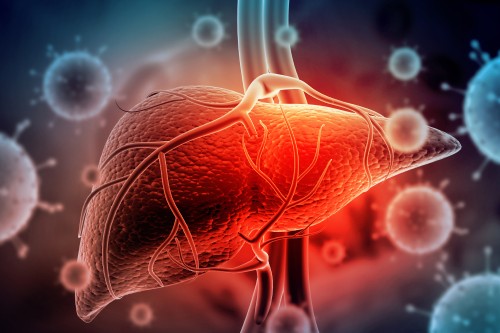
-
C型肝炎ウイルスに感染した方のうち、30%程度はウイルスが体外に排除されて治癒しますが、残り70%程度は持続感染(キャリア化)し、多くのケースでC型慢性肝炎になります。
一度慢性化すると自然治癒することはほとんどなく、そのまま放置すると肝硬変に移行し、さらに時間が経過すると肝がんへと進展します。
C型肝炎ウイルスの検査方法
C型肝炎ウイルスの感染の有無は、血液検査で確認することができます。少量の血液を採血するだけの簡単な検査で、検査結果は1週間程度でわかります。検査の流れは次の通りです。
HCV抗体検査
HCV抗体の有無を確認します。検査結果が陽性の場合、C型肝炎ウイルスに感染したことがあります。陰性の場合、基本的にはC型肝炎の心配はありません。
HCV-RNA検査
ウイルス感染持続の有無を確認します。検査結果が陽性の場合、体にC型肝炎ウイルスが存在することを意味します。陰性の場合、過去に感染したことがあるものの、ウイルスは体から排除されています。
ウイルス量・遺伝子型の測定
治療方針を決定するために、「HCV-RNA定量検査」によってウイルス量を調べたり、「ジェノタイプ」や「セログループ」などのC型肝炎ウイルスの遺伝子型を判定したりします。
肝機能・状態の確認
血液検査(AST{GOT}、ALT{GPT}、血小板など)、画像検査(エコー、CT、MRI)、必要に応じて腹腔鏡検査や肝生検などを行って肝臓の働きや状態などを確認します。
C型肝炎の治療方法
以前のC型肝炎の治療方法では、「インターフェロン(IFN)療法」「ペグインターフェロン単独療法」「ペグインターフェロンとリバビリンの併用療法」などがありますが、最近ではインターフェロンを使用しない「インターフェロンフリー療法」が主流となりつつあります。
インターフェロンフリー療法では内服だけで高い効果が期待でき、治療期間も短く、副作用もほとんどありません。
インターフェロン療法などが適応とならない方には、肝炎の沈静化を目的に「肝庇護療法」などを行う場合もあります。
現在、適切な治療を受ければC型肝炎はほとんど100%治すことが可能となっています。さらにインターフェロンフリー療法などは医療費助成の対象となり、助成を受けた場合、その方の世帯所得に応じて自己負担1~2万円程度で治療が受けられます。
インターフェロンフリー療法
インターフェロンフリー療法とは、現在、C型肝炎の主流となりつつある治療です。
ウイルスに直接作用して増殖を抑制したり、C型肝炎ウイルスを体から排除したりします。3~6ヶ月程度、毎日内服することで高い効果が期待でき、治療期間も短く、副作用もほとんどありません。
ペグインターフェロン
ペグインターフェロンとは、インターフェロンにポリエチレングリコールを結合させた治療薬で、酵素によるインターフェロンの分解を防ぐ作用があります。従来のインターフェロンよりも血中での持続時間が長く、週1回の注射で効果が期待できます。
リバビリン
リバビリンとはウイルスを攻撃する薬で、単独では効果はありませんが、ペグインターフェロンなどと併用することで作用が期待できます。
肝庇護療法
肝庇護薬を用いて肝炎を鎮静化させる方法です。
肝細胞の破壊を抑えることで、C型慢性肝炎から肝硬変への移行を抑制したり、遅らせたりすることが可能となります。